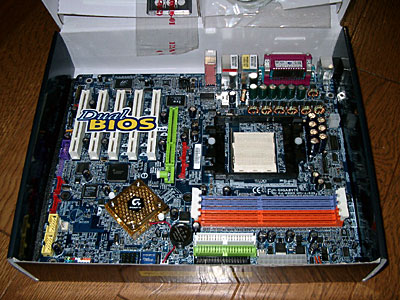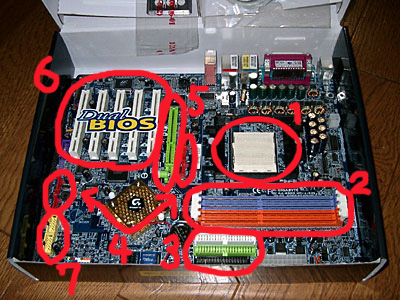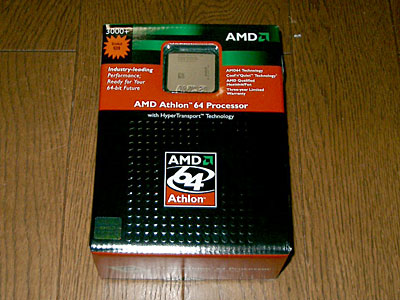| 種 別 |
メーカー |
型 式 |
特 徴 |
ケースおよび
電源 |
Scythe |
H60 (風 PHOON) |
独立ファンコン付き前後12cmファン。
前面USB×2
Scythe製 400W電源 |
| マザーボード |
GIGABYTE |
GA K8NS Ultra - 939 |
・nForce3 Ultraチップセット
・Dual Chanel DDR400 Memory
・AGP 8X
・Dual LAN (ギガビット&イーサネット)
・IEEE1394b
・シリアル ATA
・RAID 0及び1サポート
・8チャンネルオーディオ
・Dual BIOS
|
| CPU |
AMD |
Athlon 64 3000+ Socket939 BOX |
Cool'n Quiet |
| メモリ |
Hinix |
PC3200 DDR 512MB (JEDEC 準拠) |
バルク品 |
| HDD1 |
HGST(日立IBM) |
HDS722516VLSA80 (160GB SATA150 7200) |
|
| HDD2 |
SEAGATE |
ST320414A (20GB ATA100 7200) |
|
| DVDドライブ1 |
LG電子 |
GSA-4163BS |
DVD-R 16x、DVD+R 16x、DVD+R DL 4x、
DVD+RW 8x、 DVD-RW 6x、DVD-RAM x5、
CD-R x40、CD-RW x24 |
| DVDドライブ2 |
東芝 |
SD-M1502 |
DVD-ROM x16 |
| グラフィックカード |
MATROX |
Millennium G450 Dual Head |
VRAM 16MB (以前の物を流用) |
| FDD |
? |
? |
2mode |